やる気が出ないのは誰のせい?
「最近なんだか仕事に身が入らない…」「以前のように前向きな気持ちがわいてこない」
そう感じることがあるのは、あなただけではありません。
実はこの“やる気が出ない状態”には、心理学的に説明できる明確な理由があります。
人のモチベーションには法則があり、それを理解すれば、「なぜ自分や部下のやる気が落ちているのか」「どうすれば改善できるのか」が見えてきます。
今回の記事では、職場のモチベーションに関する代表的な理論である
「ハーズバーグの二要因論」と「ブルームの期待理論」をわかりやすく解説し、
実際の職場でどのように応用できるのかを考えていきます。
ハーズバーグの二要因論とは?
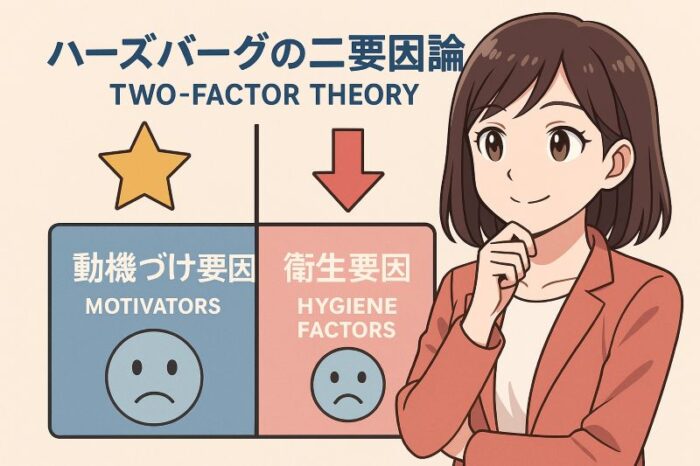
ハーズバーグの二要因論(Two-Factor Theory)は、アメリカの心理学者フレデリック・ハーズバーグ(Frederick Herzberg)が提唱した職場における動機づけと満足感の理論です。この理論では、人の仕事に対する満足と不満は、2種類の異なる要因によって決まるとされています。
「人が仕事に対して感じる満足」と「不満足」は、まったく別の要因によって生じるという画期的な考え方です。
● 満足と不満は別物?
たとえば、「給料が安い」ことで不満を感じる人がいたとします。
しかしその人に給料を上げたからといって、必ずしもやる気が高まるわけではありません。
逆に、「自分の仕事が誰かに認められた」「難しい課題をやり遂げた」といった経験は、給料とは無関係にモチベーションを高める力を持っています。
このように、「不満をなくすこと」と「やる気を生み出すこと」は別のメカニズムで成り立っているのです。
● 2つの要因
ハーズバーグは、これを以下の2つに分類しました。
衛生要因(Hygiene Factors)
これは、職場環境や待遇に関する要因で、「あって当たり前」と感じられやすいものです。
衛生要因が欠けていると強い不満が生じますが、満たされていてもやる気に直接つながるわけではありません。
例としては、給料、上司との関係、職場の安全性や清潔さ、労働時間、社内ルールなどが該当します。
いわば「土台」のようなもので、整備されていなければ不平不満が噴出しますが、それだけでは前向きなエネルギーは生まれません。
動機づけ要因(Motivators)
こちらは、仕事そのもののやりがいに関する要因です。
たとえば、達成感、周囲からの承認、新しい責任を任されたときの高揚感、成長の実感などが含まれます。
これらが満たされると、自然と「もっとがんばろう」「この仕事が好きだ」と感じるようになります。
つまり、本質的なやる気(内発的動機)を引き出すカギは、この「動機づけ要因」にあるというのがハーズバーグの主張です。
内発的動機づけ、外発的動機づけについてはこちらでも詳しく解説しています。

ブルームの期待理論とは?
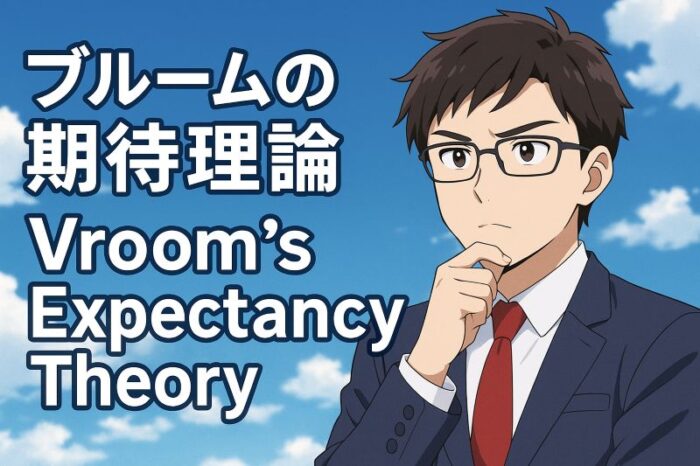
ブルームの期待理論(Vroom’s Expectancy Theory)は、1964年にアメリカの心理学者ヴィクター・ブルーム(Victor Vroom)が提唱した「人がなぜ努力するのか(動機づけのメカニズム)」を説明する理論です。
ブルームの期待理論は、ハーズバーグとは異なる角度から、人の動機づけの仕組みを説明します。
この理論の特徴は、「人は合理的に行動する存在である」という前提です。
つまり、人は「この行動をすれば、自分にどんなメリットがあるか?」を無意識に計算して動くという考え方です。
● モチベーションはかけ算で決まる?
ブルームは、モチベーションの強さは次の3つの要素のかけ算で決まると述べました。
1. 期待(Expectancy)
「自分が努力すれば、成果が出る」と信じられるかどうかです。
たとえば、営業職の人が「頑張って新規開拓をすれば、契約が取れる」と感じていれば期待は高くなります。
逆に、「どれだけ努力しても無理」と思えば、やる気は下がります。
2. 道具性(Instrumentality)
「成果を出せば、その成果が正しく報酬に結びつくか?」という信頼感です。
頑張って成果を出しても「どうせ評価されない」「上司が好き嫌いで判断する」と思っていれば、報酬と成果のつながりを感じられず、やる気は生まれません。
3. 価値(Valence)
「その報酬にどれだけ魅力を感じているか」という、報酬そのものの価値の問題です。
たとえば昇進や表彰が報酬であっても、「責任が増えるだけで面倒」と感じていれば、モチベーションにはつながりません。
● モチベーションの公式
この3要素をかけ算にすると、以下のような公式が成り立ちます。
モチベーション(やる気)= 期待 × 道具性 × 価値
この式のポイントは、「どれか1つがゼロであれば、モチベーション全体もゼロになる」ということです。
逆に言えば、やる気を高めたいなら、この3つの要素をすべて整える必要があります。
二つの理論の共通点と違い
ハーズバーグの理論とブルームの理論は、アプローチは違いますが、実は共通する点も多くあります。
たとえば、「人は単にお金や待遇だけでは動かない」という視点は共通しています。
ただし、違いも明確です。
ハーズバーグは「満足」と「不満足」を別物として扱い、やる気を高めるには仕事の中身(動機づけ要因)を見直すべきだとしました。
一方ブルームは、「人が行動を起こすまでの意思決定プロセス」に着目し、合理的な評価によってモチベーションが生まれると考えました。
また、ハーズバーグの「衛生要因」は、ブルームの理論でいうところの「価値」や「道具性」にも関係しています。
たとえば、給料という衛生要因も、報酬としての価値や、成果との結びつきが強ければ、ブルームの理論でもモチベーションに寄与するというわけです。
| 観点 | ハーズバーグの二要因論 | ブルームの期待理論 |
|---|---|---|
| 中心テーマ | 満足と不満の違い | 努力の意思決定 |
| やる気の源 | 内発的要因に重点 | 外発的要因も重視 |
| 給与の扱い | 衛生要因(不満を防ぐ) | 道具性・価値として評価 |
| 改善方法 | 成長機会や承認を与える | 成果と報酬の因果を明確にする |
職場にどう活かす?実践的なアプローチ
● 管理職・経営者の立場から
社員のやる気を引き出すには、まず衛生要因を整え、不満の原因を取り除くことが出発点です。
しかし、それだけでは「普通に働いてくれる」だけで終わってしまいます。
真のモチベーションを生み出すには、動機づけ要因に働きかける必要があります。
たとえば、仕事に裁量を与えたり、成果を正当に評価し承認したり、キャリアの成長機会を明示することが有効です。
またブルームの理論に基づいて、
「努力すれば報われる」「成果が報酬につながる」と社員に信じてもらえる制度設計と、透明なフィードバックが重要です。
● 働く個人として
自分自身がやる気を失っていると感じたときは、
「自分の努力が成果につながると信じられているか?」
「成果を出せば報酬が得られると期待できるか?」
「その報酬に本当に価値を感じているか?」
という観点から、自分の働き方や職場の仕組みを見直してみるとよいでしょう。
まとめ:やる気は「仕組み」で作れる
人のやる気は、「気合」や「根性」だけでは生まれません。
ハーズバーグの二要因論は、「やる気が出る条件」と「不満が出る原因」が別であることを教えてくれます。
そしてブルームの期待理論は、「人が動くための納得感と信頼感」の重要性を示しています。
この2つの理論を組み合わせれば、
「どうすれば人は前向きに働けるのか」という問いに対して、明確な答えを導くことができるのです。


リアクション投稿