MMTへの誤解と偏見
MMT(Modern Monetary Theory、現代貨幣理論)は、財政赤字や政府支出に対する従来の常識を覆す挑戦的な理論として注目されています。とくに「政府は自国通貨を発行できる限り、財政破綻しない」「税は財源ではなくインフレ抑制の手段」といった主張は、主流派経済学の常識と大きく異なるため、激しい賛否が巻き起こっています。
なかでも頻繁に向けられる批判が、「MMTは定量的ではない」「数字に基づく議論ができない」といったものです。しかしこれは本当に正しい批判なのでしょうか?
そこで今回は、ステファニー・ケルトンやランダル・レイらMMTの代表的な研究者による定量分析や、すでにMMT的政策を“実践”している日本や中国の事例をもとに、この批判の妥当性を検証していきます。
定量的とは?
「定量的」とは、感覚や主観に頼らず、数値やデータに基づいて論じたり分析したりすることを指します。たとえば「売上が前年比20%増加した」や「インフレ率が2%を超えた」といった具体的な数値を用いた説明が定量的です。
経済政策や理論において定量的であるとは、数式・統計・シミュレーションを通じて客観的かつ検証可能な議論ができることを意味します。
MMTとは何か?基礎理論の整理
まずはMMTの基本的な主張を整理しておきましょう。
これらを正しく理解していないと、後述する定量的議論も見誤ることになります。
MMTの主な前提
- 政府は自国通貨建てで借金できる限り、財政破綻しない。
- 税金は政府支出の「財源」ではなく、インフレ調整・格差是正のためのツールである。
- 財政赤字は民間の黒字(貯蓄)の裏返しであり、必ずしも悪ではない。
- 政府には完全雇用を達成する責任があり、「Job Guarantee(雇用保証制度)」を通じてそれを実現すべきである。
MMTはこのように、通貨の供給構造と財政の役割を主流派経済学とはまったく異なる視点から再定義しているのです。
「MMTは定量的でない」と言われる理由
MMTはなぜ「定量的でない」と批判されるのでしょうか?その根本には、主流派経済学とMMTの“モデル”の違いがあります。
主な批判ポイントとその背景
| 批判点 | 背景・理由 |
|---|---|
| インフレの予測が難しい | 政府支出の上限を「インフレになるまで」としているが、その閾値が不明瞭だとされる |
| 均衡モデルを採用しない | IS-LMやDSGEなど、従来の静的均衡モデルを使っていない |
| 政策の時間差を軽視している | インフレが出た後に増税で対応という考えに“遅すぎる”との批判 |
| 金融市場の反応を過小評価している | 国債発行が金利や通貨価値に影響を与えるという前提がない |
しかし、これらの批判は「MMTが定量的な分析をしていない」ことを意味するわけではありません。むしろ、「主流派の定量モデルに従っていない」だけなのです。
補足解説:IS-LMとDSGEとは?
◆ IS-LMモデルとは?
IS-LM(Investment-Saving / Liquidity preference-Money supply)モデルは、ケインズ経済学に基づいた短期マクロ経済モデルで、財市場と貨幣市場の均衡関係を描きます。
- IS曲線:民間投資と貯蓄のバランス(財市場)
- LM曲線:貨幣需要と供給のバランス(貨幣市場)
- 両者の交点が「均衡利子率」と「国民所得(GDP)」を示す
政府支出や金利政策の短期的効果を視覚的に分析できますが、価格の硬直性や通貨制度の現実をうまく扱えないという限界があります。
◆ DSGEモデルとは?
DSGE(Dynamic Stochastic General Equilibrium)モデルは、現代の主流派経済学が用いる数理モデルで、将来予測を含んだ動学的分析が可能です。
- 経済主体は「合理的期待」に基づいて行動
- 経済全体は「一般均衡」に向かうと仮定
- 政策変更の影響を「ショック」として確率的に扱う
しかし、現実の経済に存在する不確実性・通貨制度・不完全競争などを十分に再現できないため、MMTを含む批判派からは「抽象的すぎて現実と乖離している」と指摘されています。
MMTの定量分析:ケルトンとランダル・レイの仕事
ケルトン:『The Deficit Myth』に見るセクター収支の視点
ステファニー・ケルトンは著書『The Deficit Myth』の中で、財政赤字を「民間の黒字」として再評価する“セクター収支(Sectoral Balances)”の枠組みを提示しています。
たとえば、
政府の財政赤字 = 民間部門の黒字 + 海外部門の黒字(経常収支)
という恒等式をベースに、財政赤字がそのまま民間貯蓄の源泉であることを、米国の国家経済計算データ(NIPA)から実証的に導いています。これは感情論ではなく、実証データに基づいた構造的定量分析です。

ランダル・レイ:Job Guaranteeの財政試算
ランダル・レイは、MMTにおける最も特徴的な政策である「Job Guarantee(雇用保証制度)」の定量モデルを構築しました。
- アメリカの失業者約1,500万人を年間2万ドルで雇用すると仮定した場合、必要な予算は約3,000億ドル(GDPの1.5%)
- 同時に、失業保険や生活保護支出の削減、税収増加により財政赤字は実質的に縮小
- Levy InstituteのWorking Paperなどで詳細な数値モデル・シミュレーションが提示されている
こうしたシミュレーションは、MMTが単なる「思想」や「スローガン」ではなく、具体的な政策としての設計可能性を持つことを示しています。

日本と中国:MMT的政策の“実証済み”モデル
MMTは「机上の空論」ではなく、すでに日本や中国で“知らずに”実行され、その効果が現実に現れています。
日本:巨額赤字でもインフレなし、金利ゼロ
- 政府債務残高はGDP比260%(世界最大)
- 10年国債金利は0%台で安定
- インフレ率は長年ゼロ〜1%程度のデフレ圧力
- 日本銀行が国債の半分以上を保有(=事実上の貨幣発行)
このような状況は、MMTが主張する「財政赤字=破綻にはつながらない」「インフレが起きない限り支出余地がある」をそのまま体現しています。
中国:政府主導の資金供給で成長牽引
- 地方政府を通じたインフラ投資、銀行融資の誘導
- 中央銀行のコントロール下にある国有銀行システム
- 通貨価値や金利は政府主導で安定
中国は、MMT的な「国家による需要創出と信用供給」のモデルを意図的に運用しており、それによって高い経済成長と雇用維持を両立させています。
中国経済の減速とMMT的政策の限界──理論と現実のギャップ
中国は過去にMMT的アプローチで大きな成果を上げてきましたが、現在では経済減速が顕著になっています。この減速がMMTの限界を示しているのか、それとも他の構造要因によるものかを考察します。
- 不動産依存型経済モデルの行き詰まり
- 地方政府と民間開発業者の過剰債務
- 若年層失業率の高止まり(20%超)
- 内需不足と民間消費の冷え込み
これらはMMTの原理的枠組みではなく、政策実行の精度や経済の構造的問題に起因するものです。したがって、中国の失速はMMT理論自体の失敗ではなく、その「応用設計」の不整合や、「Job Guarantee」など雇用面の制度未整備といった実装上の課題に起因しています。
それでも、過去20〜30年にわたり数億人を貧困から引き上げたという点で、中国にとってはMMT的政策は“戦略的には成功”と評価することも可能です。
否定派はなぜ反論し続けるのか?
MMTの理論的・実証的な整合性が示されているにもかかわらず、多くの経済学者やメディアはこれを否定し続けます。なぜでしょうか?
原因1:家計簿的財政観の信仰
多くの人々が、「政府も家計と同じようにやりくりすべきだ」という直感に囚われています。しかしMMTは、政府は通貨の発行主体であり、家計とは根本的に異なる存在であると見ます。しかしこれはミクロ経済とマクロ経済をごちゃまぜに考えているからであり、家計(ミクロ)と中央銀行のある国家(マクロ)は切り離して考えなければなりません。
政府と家計は同じか?──ミクロとマクロの混同
「政府も家計と同じようにやりくりすべきだ」という主張は、日本の政治・報道・経済教育において広く共有されています。しかしこの考え方は、ミクロ経済(家計や企業)とマクロ経済(国家や政府)を同一視する誤りに基づいています。
◆ 家計は通貨の「使用者」、政府は「発行者」
- 家計や企業は、限られた収入の中でやりくりをする「通貨の利用者」です。
- 一方で、政府は自国通貨を発行できる唯一の存在であり、支出の制約条件が根本的に異なります。
この違いを無視して「借金=悪」「黒字=善」と短絡的に考えると、必要な公共投資や景気対策まで制限され、かえって経済を悪化させる可能性があります。
◆ MMTの視点:政府はマクロ経済の「供給者」
MMTでは、政府は「最終的な貨幣の発行者」として、雇用や需要の不足を補う責任があると考えます。家計と違って、通貨を発行し、支出によって経済全体の需要水準を調整する立場にあるのです。
ミクロとマクロの違いを理解することは、MMTだけでなく、現代経済全体を考える上でも極めて重要な出発点となります。
原因2:インフレ恐怖症
過去のハイパーインフレ(例:戦前のドイツやジンバブエ)を引き合いに、「通貨発行は危険だ」という認識が根強い。しかし、これらの事例は供給能力の崩壊や戦争が原因であり、MMTの前提とは異なります。
「通貨を発行すればハイパーインフレになる」という主張は、歴史的な極端な事例──たとえばジンバブエや戦間期ドイツなど──を根拠に語られることが多いですが、日本のような国においてはまったく現実的ではないというのがMMTの立場です。
◆ 日本は主軸通貨を担う国である
日本円は国際的な主要通貨の一つであり、円建て国債は世界中の投資家から信用されています。通貨の信認が高いため、ある程度の政府支出・通貨発行を行っても、為替暴落や物価暴騰に直結しにくいという特徴があります。
◆ 日本の供給能力は非常に高い
MMTは「供給能力がある限り、支出増はインフレを引き起こさない」とします。日本はインフラ・技術・労働力の面で高い供給能力を維持しており、デマンドプル型のインフレすら長年起きていません。むしろ慢性的なデフレ傾向にあり、「通貨発行による制御可能なインフレ」が必要な状況です。
◆ 恐怖ではなくデータで判断すべき
「ハイパーインフレになるかもしれないから財政出動をやめよう」という議論は、恐怖心に基づいた政治的レトリックにすぎません。冷静にデータと制度設計を踏まえれば、現在の日本において通貨発行=暴走インフレという発想は、根拠が乏しい非論理的なものだといえます。
原因3:主流派経済学の既得権益
大学、中央銀行、IMFなどの機関では、主流派モデルが“標準”とされており、MMTのような理論は受け入れられにくい構造があります。理論の正しさ以前に、制度的な抵抗があるのです。
主流派経済学と“ディープステート”の構造的類似
MMTがなかなか社会に受け入れられない背景には、主流派経済学の「既得権益構造」が強固に存在しているからだと指摘されています。この構造は、しばしば“ディープステート”と呼ばれる政治・官僚・金融エリート層のネットワークと類似しています。
◆ 学問の権威構造と通貨観の固定化
大学・中央銀行・国際機関(IMFや世界銀行)などでは、主流派経済学(とくにDSGEモデルを中心とする新古典派理論)が「正統」として扱われています。このため、異端とされるMMTのような理論は制度的に排除されやすく、学会・メディア・教育現場でも“無視”される傾向があります。
◆ ディープステート的な官僚機構との共鳴
政府内の財務官僚や国際金融ネットワークは、緊縮財政や均衡財政を正義とする通貨観を共有しており、これが既得権として固定化されています。結果として、「財政赤字=悪」「インフレ=敵」という通念が、あたかも不動の真理のように政治を支配しています。
この構造は、情報の独占・政治的影響力・教育支配といった“ディープステート”と呼ばれるネットワークの構造的特徴ときわめてよく似ており、MMTを真正面から議論させない力学がそこに働いていると考えることもできます。
まとめ:MMTは定量的であり、すでに現実に機能している
MMTは「定量的でない」というより、「従来の定量モデルに乗らない」だけです。そして日本や中国では、すでにMMT的政策が現実に運用されており、破綻や深刻なインフレも起きていません。
ケルトンやWrayの研究、Levy Instituteのシミュレーション、そして何より日本経済の実例が、それを証明しています。
もはや「信じるか信じないか」ではなく、「現実を見るかどうか」が問われているのです。

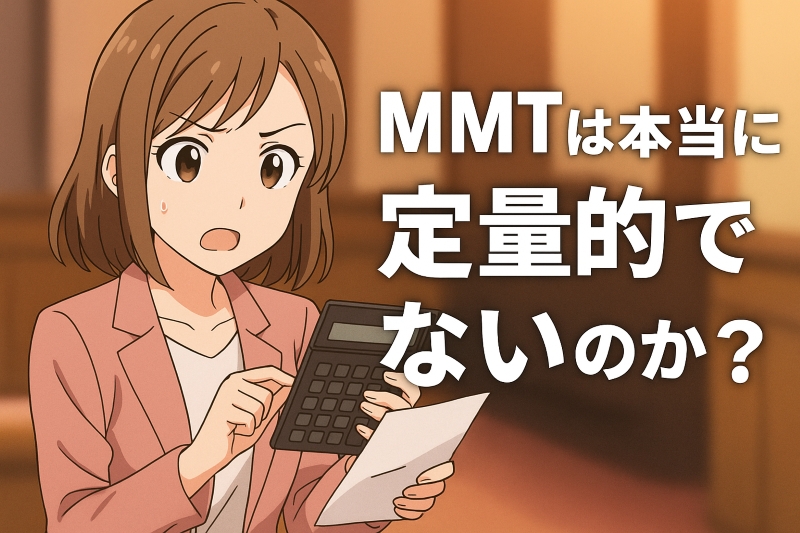

リアクション投稿