ものづくり補助金の申請と書き方
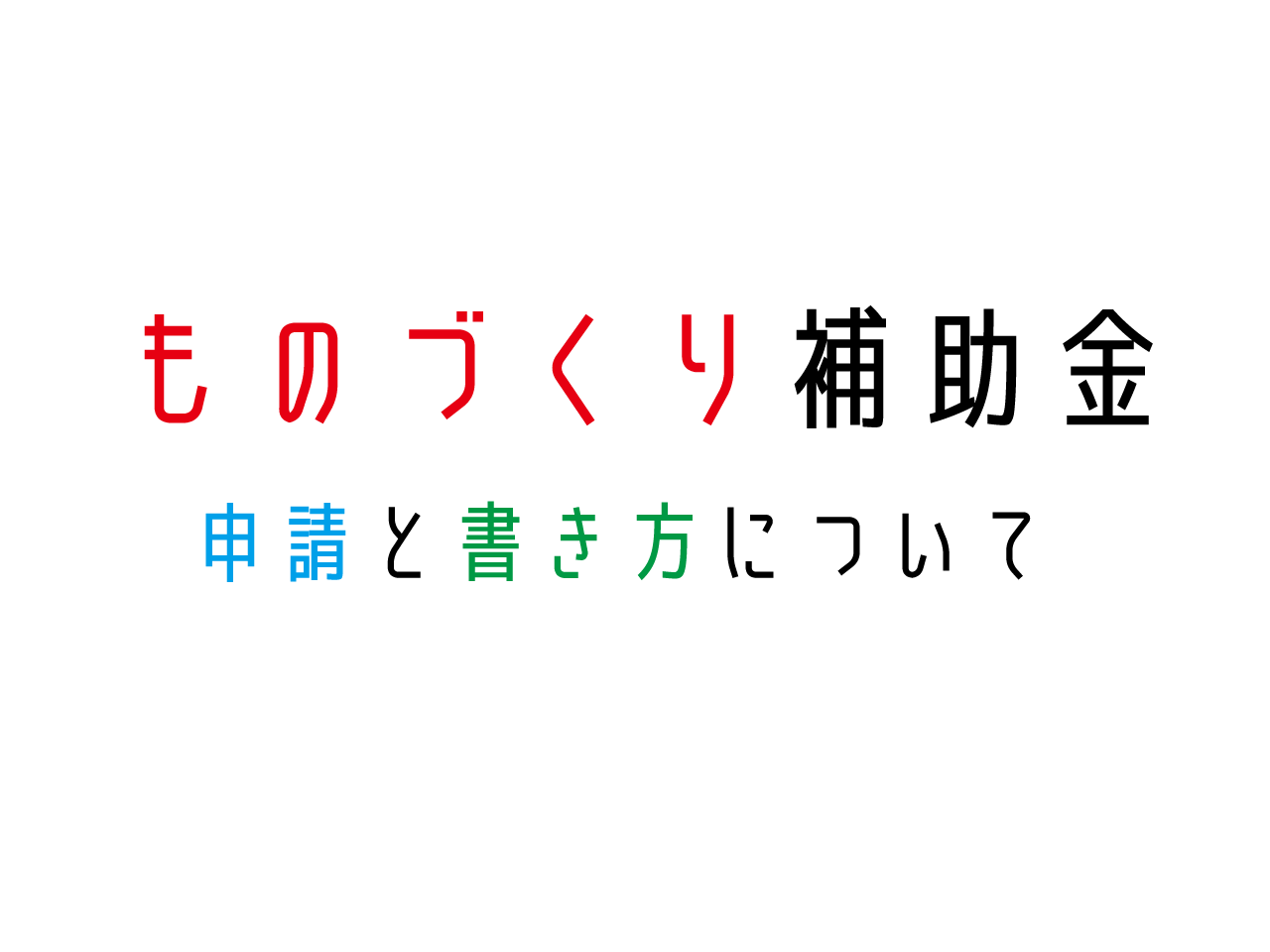
ものづくり補助金とは、革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を講じる
中小企業や小規模事業者に向けて、補助率1/2もしくは最大2/3を補助金として受領できる制度です。
補助金なので無利子・返済不要、つまり国からもらえるお金なので、とても人気を集めています。
補助金を受けるには所定の書類に必要事項を記入して提出し、審査に通過しなければなりません。
この確率はおよそ50%と言われていますので、安易に体裁を整えるだけでの書面では審査に通るのは難しいと考えられます。
以下に、ものづくり補助金の書き方や申請方法をまとめてみましたので、今後の参考としてみてください。
ものづくり補助金申請にあたり、まずは「GビズIDプライムアカウント」の取得が必須です。取得されていなければ、会社の印鑑証明等を揃え、申請の手続きをしましょう。詳しくは下記サイトへ。
分かりやすい内容であることが前提
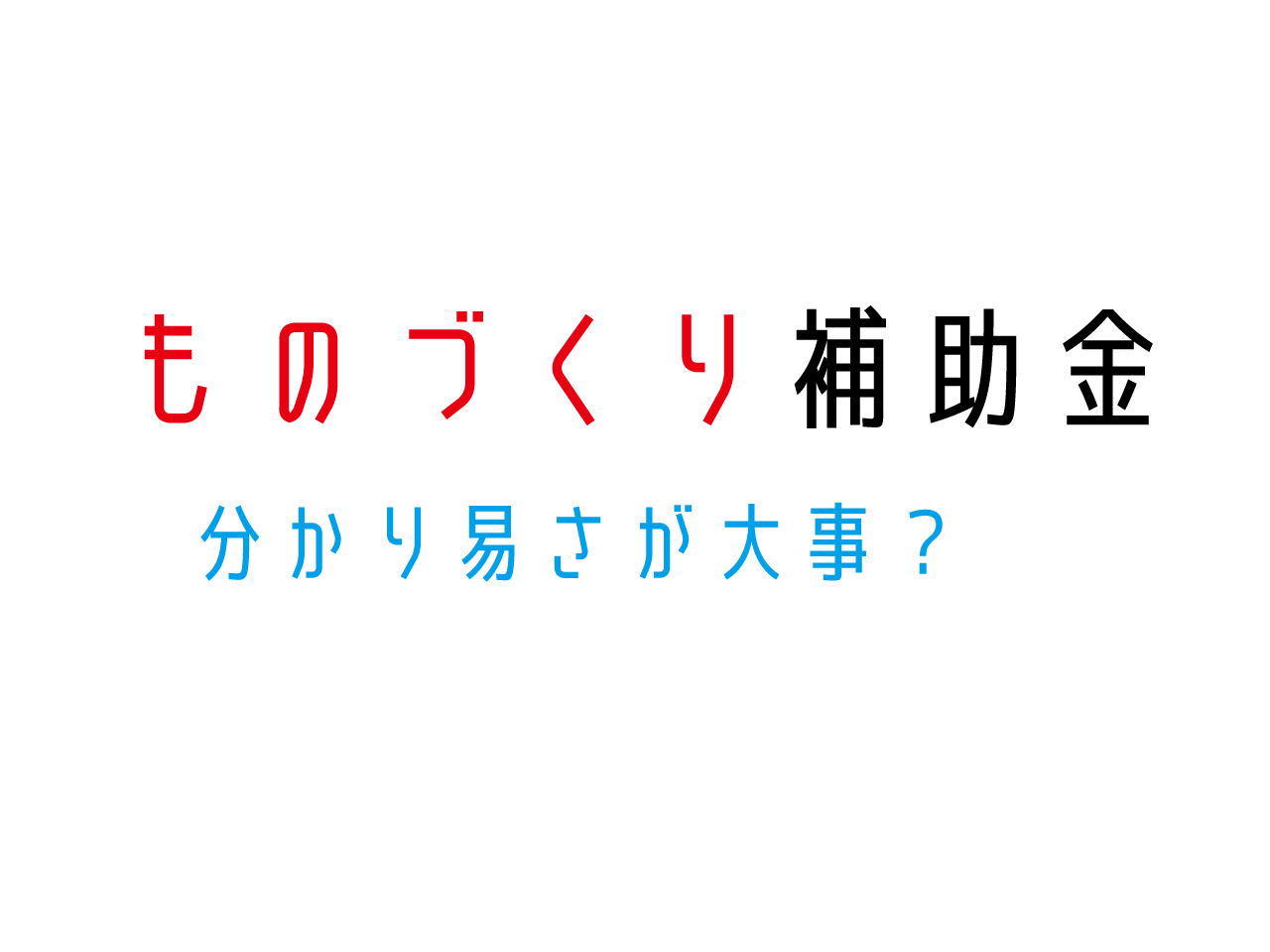
ものづくり補助金は所定の様式に沿って必要事項を記入していくわけですが、まず念頭に置くべきは採択されやすい内容とすることです。
そのためには、誰もがわかりやすい内容でなくてはなりません。
複数の審査担当者の目に触れるわけであり、専門性を持った担当者もいれば、そうでない担当者もいるだろうことを考えれば、納得いただけるのではないでしょうか。
銀行へ融資申し込みする際の書面同様であると考えたほうがわかりやすいかもしれません。
つまるところ、審査担当者が、提出書類に記載された事業内容について納得し、それが成功するだろうと思えば、ものづくり補助金が得られるようになるのです。
分かりやすく補助事業と関連させること
会社概要については、事業者の名称、資本金、従業員数、業種などの登記簿に記載されているような事項はすぐに埋められるでしょうが、自社が現在どのような事業を営んでいるのかを説明する欄は、複雑すぎず長くなりすぎず、審査員に伝わりやすい言葉を選びながら記入するようにしましょう。
記入のコツとしては、ものづくり補助金に申請する補助事業と密接に関連させるように入れ込んでいくことです。
その理由は、本業の周辺に位置する事業であると判断されれば、それだけ成功する確率も高いだろうと判断されやすいためです。
どのような業界であってもそうですが、新規事業として周辺事業と考えられる範囲へと進出したほうが事業基盤を兼用できることから、自ずと成功する確率は高まります。
やや保守的なように思えるかも知れませんが、補助金は国庫金の支出に他ならず、その交付にあたっては保守寄りの考え方であると思っておいた方がいいのです。
上で銀行への融資申し込みの例を出しているのも、保守的であるとの共通点があるためです。
目標値や優位性の具体的な記述を
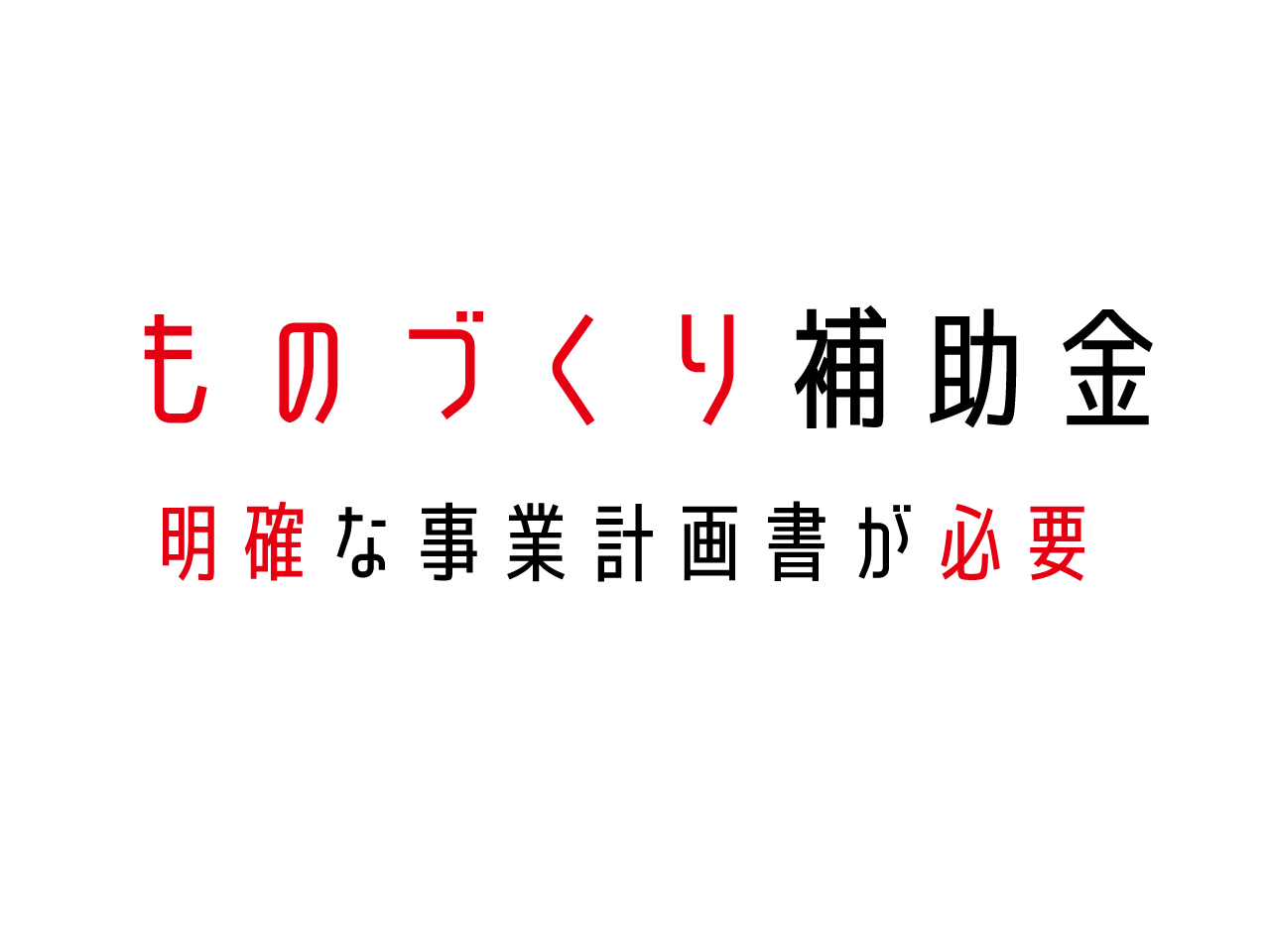
そして、ものづくり補助金の本質に迫る内容を記入し始めていくわけですが、まず注意すべきは“補助事業の目的とその背景”についての記述です。
ちょっとややこしいかもしれませんが、補助金が欲しいから補助事業に着手すると思われないよう、補助事業に必要だから補助金の申請をする、という流れを徹底しなければなりません。
加えて、その裏付けとして、
“経営の目標値”や“本事業を遂行することで得られる自社の優位性”について具体的な記述をしていきます。
どのように会社の数字に変化が生じて、どれだけの競争力が得られるようになるのか、リアリティーが伴うように記入していく必要があります。
数字について付け加えるならば、資金計画についてはカツカツな内容で記述しても現実味がないと判断されます。
なぜなら、ものづくり補助金は申請し、採択されても事業を実施して半年後ぐらいでないと補助金は振り込まれません。補助事業にかかるコストを一時的に立て替えるため、その期間内に資金がショートしそうな書類としてしまえば、審査に通過するものも通過しなくなってしまうことでしょう。
様々なデータを駆使することで信憑性を上げる
最後に、ものづくり補助金は将来の企業成長を促すことも目的としているのですから、
どれほど収益性がアップするのかも含めなければなりませんし、自社の独り善がり的な内容とすべきではなく、市場調査した結果も盛り込むべきといえます。
例えば、補助事業の対象となる市場の規模はどのぐらいなのか、民間の調査会社のデータや、各金融機関発表のレポート、経済産業省が公表している統計データを使えば、申請書類の信ぴょう性を上げることができます。
審査担当者に分かりやすい構成であること
書類をすべて書き終えたら、所定の宛先へと郵送するわけですが、用紙を綴ったファイルを送付するのもOKですし、USBに格納して送付するのも認められています。
ただし、どちらの場合であっても留意すべきは、
審査の担当者に必要な書類を探させることの内容、わかりやすい構成とすべき点です。
審査担当者は全国から送られてきた膨大な数の申請書類に次々と目を通さなければならないので、構成ファイルが分かりづらいだけでも審査対象としてもらえないリスクが考えられるためです。
これらをクリアするためには、
“目上の人に提出する、失敗の許されない書類”であると考えていた方がいいかもしれません。
申請書はコンサルタントに任せた方が良い?
最後に、ほとんどの方々が申請にはコンサルタントにお任せするのが多いかと思います。そこで、改めてコンサルタントにお任せしたほうが良い理由を以下に挙げてみたいと思います。
- 専門知識:補助金の申請は複雑であり、専門的な知識が必要です。コンサルタントはこれらの申請に関する経験や知識を持っているため、正確な手続きを進めることができます。
- 時短:補助金の申請書類の作成や手続きには非常に多くの時間がかかります。専門家に依頼することで、自身の仕事を犠牲にせず効率的に申請を進めることができます。
- 申請の品質向上:コンサルタントは過去の経験から、申請の際に何を重視すべきか、どのように書類を作成すべきかを知っています。そのため、受給確率を上げるための高品質な申請書類の作成が期待できます。
- 失敗リスクの低減:間違った手続きや情報の不足、締め切りの過ぎ逃し等、申請に関するミスは補助金を受けるチャンスを逸してしまいます。コンサルタントのサポートにより、これらのミスを避けることができます。実際の不採択になるケースも書類の記入漏れや不足が最も多いと聞きます。
- 最新の情報:補助金の内容や申請要件は変わることがあります。コンサルタントは常に最新の情報をキャッチしており、その情報をもとに最適な申請をサポートしてくれます。
- 効果的な計画策定:補助金の取得後の使用計画やビジネスモデルの策定もコンサルタントの専門分野です。適切なアドバイスにより、補助金を最も効果的に活用することができます。
- サポート体制:不明点や疑問点が生じた際、迅速に対応してくれるのもコンサルタントの大きなメリットです。
これらのメリットを考慮すると、補助金の申請に関してはコンサルタントに任せる方が効率的で確実性が高まることがわかります。ただし、コンサルタントの選定には注意が必要であり、信頼性や実績をしっかりと確認することが推奨されます。
以上を参考に、皆さんもものづくり補助金の受給申請に取り組んでみてはいかがでしょうか。
